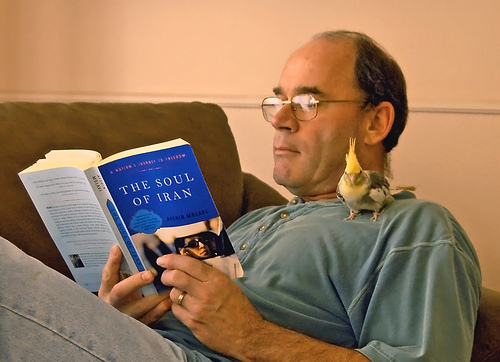
photo credit: gwilmore via photo pin cc
こんにちは柬理(かんり)@keikanriです。
実は私は日々おもしろく、そしてわかりやすいエントリーを心がけています。最近はサラリーマンを辞めるまでという割とシビアな内容を書いたりしていますが、できるだけユーモア溢れてわかりやすい文章になる様になる様に文章を愛でてる訳です。
友人のブロガーからはスベリ芸と言われヘコんだりする訳ですが、日々エントリーをおもしろくする為に私は精進しているのです!
ある日もわかりやすくおもしろい文章を書こうと本屋で何か参考になる本はないか!っと彷徨っていました。
新越谷駅にある本屋での私のエンカウント率の高さは本当に驚くべき事です。私に会いたければ新越谷駅に是非お越しください。
しかし、「わかりやすい文章云々」の本はどれを見ても「主語、述語!云々」「起承転結云々」「接続詞を云々」と学生時代国語が嫌いだった私にはあまり面白い本がありません。
そんな時に異才を放っていた本がありました。それは小田嶋隆氏の著書
『小田嶋隆のコラム道』
帯を見ても「なんだかわからないけどめちゃくちゃおもしろい。」と書いてありますし、コラムとブログじゃちょっと違うけど同じ文章ですし、この本で面白い文章の神髄を学んでやろう!と即刻購入したのです。
コラムニストが伝授するおもしろい文章を書く為のコツ4つ!

photo credit: miuenski via photo pin cc
結果としてこの本は非常に面白い本でした。何が面白いのかというと小田嶋氏の文章が非常に面白い!!
普通の視点からちょっとずらしてそして必ずオチを付ける。そしてオチまでに何回か軽くも落としておく。
っといった手法で読者を楽しませます。
今回はこの本で私が大事だなと感じた文章のコツ(あまりこう書いた方がいい!!みたいな部分はなかったのですが)4つを書いていきます。
1.書き続ける事でモチベーションを維持する
まず面白い文章云々よりも文章は書き続けてどんどんアウトプットしていかなくてはいけません。特に私の行っているブログではね。
よくブログをやっていない友達から
「毎日書く事って大変じゃないの?」
なんて聞かれます。「えぇ実は結構大変です。」
しかし、2ヶ月3ヶ月休んだら面白い文章が書けるかというとそんな事もない様な気がします。
この本でも記載されていますが、モチベーションは書き続ける事で維持できると。書き続ける事で様々なアイディアが思い浮かびそこから書きたいネタがどんどん出来てくるんです。
面白い文章のテクニック的な事とは関係ないのかもしれませんが、文章を書き続ける上では必要な考え方ですね。
2.書き始めにこだわる必要はない
書き始めインパクトをガシッと与えようと考える事はブログでもよくある事です。
「恥の多い生涯を送って来ました。」
「吾輩は猫である。名前はまだ無い。」
なんて書き出しを書けたらカッコいいですしね。
しかし、この本を読むと意外な事を突き付けられます。
「読者にとって書き出しは以外とどうでもいい」
っと。
読み始めたら書き出しの事なんて忘れている。伝えたい事が伝えられていれば書き出しなんて書き終わった後にいくら変えたって何したって構いはしません。
上記でも書いたモチベーションを保つ為には書き続けるしかありません。それを書き始めで詰まっている暇はないのです。
3.推敲は書き終わった後に
文章を書いている時と読んでいる時に必要とする能力は別物です。
書く時には独創性やユーモア性などが大事でしょう。読んでいる時は客観性などが大事になってきます。
なので書きながら推敲する事はあまり良くない訳です。
書き終わってから一息ついて(お風呂に入るでもなんでも)推敲してみると
「こんなの恥ずかしくて公開できない!!見事にスベッてる!!」
なんて事もあるでょう。ラブレターは夜書いたら次の朝に読み直せ。先人達は良く言ったものです。
4.主語がキャラクターを作る
文章にキャラクター性を持たせる事があります。私の友人でも大胆なキャラクターと素晴らしい内容で人気を博しているブロガーがいます。
この本には主語でキャラクター性の大半は決まるという事が記述されています。
例を出しましょう。
私が
⇒んーなんかフォーマルですね。
僕が
⇒青年って感じですね。
ボカァ
⇒大きい!!なんか器が大きい!!
拙者が
⇒よっ!!江戸の方!!
自分が
⇒なんか多分筋肉ムキムキか。それか不器用か。
この拳王が
⇒うん。お前ラオウだな。
どうでしょうか。主語を変えてキャラクター性を付けるのも面白いのではないでしょうか。
.png)

コメントはこちらへ!